製本と紙のはなし
更新日:2014年2月1日
印刷された紙がばらばらに散在している状態では、「本」とはいえません。これらをひとつにまとめて、つまり「製本」して、はじめて「本」となります。
このコーナーでは、そんな製本についてのお話を集めました。ついでに、紙のことにも触れています。
製本
本製本(ほんせいほん)
上製本(じょうせいほん)ともいいます。本の中身とは別に表紙をつけて製本する方法。通常はボール紙など(板紙)の厚表紙ですが、辞書のように薄い素材を使ったものもあります。
並製本(なみせいほん)
仮製本(かりせいほん)ともいいます。表紙に厚表紙を使いません。板紙を用いた本をハードカバーというのに対して、ペーパーバックといいます。中身に表紙をつけてから仕上げ裁ちしますので「チリ」がありません。
背の形
通常、洋装書では「針金綴じ」でなければ、薄紙やクロースで「背貼り」をし、さらに「背文字」の入った「背表紙」を付けます。背の形あるいは作り方によっていろいろな名前で呼ばれています。
タイト・バック
硬背(こうぜ・かたぜ)、堅背(かたぜ)ともいいます。本の中身と背表紙を密着させたもの。開きにくく、判型によっていたみやすいようです。
フレキシブル・バック
柔軟背(じゅうなんぜ)、柔背(じゅうぜ)、軟背(なんぜ)ともいいます。本の中身と背表紙を薄紙などを介して密着させるものです。
ホロー・バック
本の中身と背表紙を密着させずに、本を開いたときに隙間を作る形。腔背(あなぜ・こうぜ)ともいいます。一般的に用いられ、本を見るとき開きやすく、いたみにくいといわれています。
平背(ひらぜ)
背の形が平らなもの。

丸背(まるぜ)
背の形が丸いもの。幅の広い資料や版型の小さな資料は「丸背」の方が形がくずれず、繰り返しの利用に耐えると考えられています。
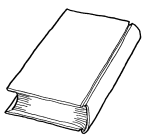
丸背の製本のしかた
- 本の天と地にぐるっと帯をかけて固定します。
- 小口(前小口)を手前にして、親指で押し込み丸みをだします(丸み出し)。
- げんのうまたは金槌などで軽く叩いて落ちつかせます。
- 帯を少し斜めにずらして丸みがずれないようにします。
- 丸みを出したままでは形を維持しにくいので、山をたたいて形を整えます。(背たたき・バッキング)この膨らみが落ち込んだ部分に表紙のみぞが入り、本を開きやすくします。
- しおり、はなぎれ、喉布、表紙の順に貼りつけて完成。
ページ
丁(ちょう)
和本では2ページ1枚をさしますが、洋装書では「折丁」のことをいいます。
折丁(おりちょう)
全判か半裁した紙を何回か折りたたんで作ったもの。普通は8つ折り16ページが標準。これをいくつも重ねて本にします。また、折った時にページのようになっていない部分を袋といい、後に切断します。
各折丁には背に折記号が印刷されていて、製本の際に順番を間違えない工夫がされています。折丁の順序を間違えたためにおこるページの順序が違うものを「乱丁」、折丁がひとつ落ちているものを「落丁」といいます。
綴じ方
(1) 綴じる道具による分類
糸綴じ(いととじ)
紙を糸で綴じていきます。こうしてできた本を線装本ともいいます。
針金綴じ(はりがねとじ)
紙を針金で綴じます。
無線綴じ(むせんとじ)
紙を糸や針金を使わずに、直接糊づけして綴じたもの。
(2) 綴じる方法による分類
打抜綴(うちぬきとじ)
一冊分の紙葉を重ねて、平(ひら)の「のど」の部分に穴を開けて、糸・針金で綴じます。和装書のほとんどはこの綴じ方です。洋装書では、「のど」の開きが悪くなるのが欠点です。
鞍型綴(くらがたとじ)
一冊全体がひとつの折り丁になっていて、折り目の線で糸・針金で綴じていきます。週刊誌などの雑誌に多い綴じ方です。また、最近は、簡易製本機などで背が金属でできており左右から圧力をかけて、はさみこむ形で製本するタイプもあります。
2.紙の種類と特徴
本は紙に印刷されていますが、単に紙といっても多くの種類があり、さまざまな用途に使われています。
名称もさまざまで、用途によって「印刷用紙」「図画用紙」「障子紙」がありますし、人名による「せんか紙」、原料名によっては「コウゾ紙」・「麻紙」があります。製造方法によれば「硫酸紙」・「パラフィン紙」、紙質による「上質紙」・「中質紙」、厚紙・薄紙のように厚薄によって分けることもできます。そのほかにも色による名称があります。
ちなみに、英語Paper は、アフリカ原産の大型の多年草Papyrus(パピルス)が語源といわれています。パピルスは、アシに似た草で、茎の軸を裂いて縦横に編んだものを紙として使用していました。古代エジプトでは、ボート、衣料にも使用していたということです。
目
紙を構成する繊維の向きを目といいます。目は製造工程で、紙料が進行方向に向かって脱水されることによって、縦に行列するように繊維が結合してできます。
裁断された長辺に目が通っているものを「縦目」、短辺に目が通っているものを「横目」といいます。普通、本を作るには本文、「見返し」とも縦目の紙を使います。縦目の紙はページを開けたときに(縦に繊維が通っているため)開きやすいためです。逆に横目の紙を使うと開きが悪くなり、こわれやすくなります。
さて、余談ですが目の見分け方としては、紙を軽く折り曲げてみる方法があります。曲がりやすい方向が目になります。その他に、透かしてみる、破いてみる、水につけて曲がりをみる、2方向に短冊に切って端を持って垂らすなど、さまざまな方法がありますが図書館の本では試さないでください。
また、繊維の結合状態を「地合」といい、繊維の均一に絡み合い強さがあって、印刷しやすいものを地合の良い紙、結合が弱くアンバランスなものを地合の悪い紙といいます。
大きさ
紙のサイズ(表記の順序:先に紙幅、後ろに長さの順にあらわします)。縦目の方向が長さになりますので、横寸法が縦寸法よりも長いものは横目の紙ということになります。
| A列本判 | 625× 880mm |
| B列本判 | 765×1085mm |
| 菊判 | 636× 939mm |
| 四六判 | 788×1091mm |
| ハトロン判 | 900×1200mm |
A・B列本判はそれぞれA1・B1にあたりますが、紙加工サイズの方が少し小さいのは、印刷過程で機械に紙を送るツメのかかる部分(くわえ)があるためです。
通常私たちは紙加工仕上げサイズ(既に規格の大きさに切断してある)の紙に印刷をしますが、印刷会社などでは加工前サイズに印刷後、化粧断ちするためにサイズのずれが生じます。
紙加工仕上げサイズ
| A0 | 841×1189mm |
| A1 | 594× 841mm |
| A2 | 420× 594mm |
| A3 | 297× 420mm |
| A4 | 210× 297mm |
| A5 | 148× 210mm |
| A6(文庫本) | 105× 148mm |
| B0 | 1030×1456mm |
| B1 | 728×1030mm |
| B2 | 515× 728mm |
| B3 | 364× 515mm |
| B4 | 257× 364mm |
| B5 | 182× 257mm |
| B6 | 128× 182mm |
| 四六判 | 127× 188mm |
| 菊判 | 152× 218mm |
| ポケット判 | 72× 152mm |
| 菊袖珍(きくしゅうちん)判 | 109× 148mm |
| 四六袖珍判 | 90× 127mm |
| 三六判(A判40取・新書判) | 90× 177mm |
| 三五判(A判40取) | 84× 148mm |
| A判20取 | 167× 148mm |
| B判20取 | 206× 182mm |
製本の項で述べたように、チリのある本は紙加工仕上げサイズより本の方が少し大きくなります。
| 半紙判 | 242× 333mm |
| 美濃判 | 273× 394mm |
| 大奉書 | 530× 394mm |
| 中奉書 | 500× 364mm |
| 小奉書 | 470× 333mm |
酸性紙(さんせいし)
印刷のインクのにじみを防ぐサイズ剤に酸性剤を用いたために、紙の劣化を起こしやすい紙。日本では、昭和10~30年あたりの紙が特にひどく、触るだけで粉々になるものもあります。図書館・文書館など多くの資料保存施設で頭をいためている問題。中之島図書館でも資料の傷みが少ない複写機の導入や、傷んだ資料の複写の制限を行っています。
