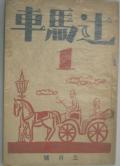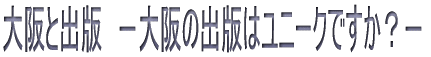平成18年度 中之島図書館 文化講演会
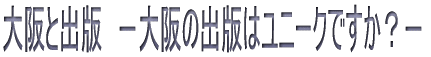
《講演会は終了しました》
いま関西・大阪の出版は下火ですが、明治以降、近代の大阪にはユニークな出版社と出版人がいました。彼等の中には冒険的出版人も、趣味の世界に遊んだ人もいました。玉石混交の出版世界から、ユニークな出版物や出版人を取り上げ、大阪の出版史を振り返り、大阪と出版というテーマを再考します。
|
|
|
| 「雑誌“辻馬車”と波屋書房の周辺」 〜大阪出版史の一齣(ひとこま)〜
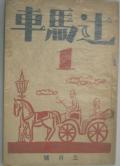
講師:林 哲夫 氏
プロフィール: 1955年、香川県生まれ。画家・文筆家。著書に『文字力100』、『歸らざる風景−林哲夫美術論集』(みずのわ出版)等。2002年『喫茶店の時代』(編集工房ノア)で第15回尾崎秀樹記念大衆文学研究賞受賞。
|
|
大正14年、雑誌「辻馬車」は、文学を志す藤沢桓夫、小野勇、神崎清等に波屋書房の宇崎祥ニが協力するかたちで出来上がった若者達による文芸雑誌である。若人たちの新鮮で真剣な文学と出版への思いと、関わった人々の人間模様を通じて大正から昭和時代の大阪出版史の一齣についてお話いただきます。
|
|
|
「三好米吉とは何者か?」〜雑誌「柳屋」と近代の大阪出版界を考える〜
講師:熊田 司氏

プロフィール: 1949年、兵庫県生まれ。大阪市立近代美術館設立準備室研究主幹。主に日本近代の美術史を研究、関連の出版史・印刷史にも関心を寄せる。『美術フォーラム21』、『大阪の歴史と文化財』等に論文を発表。
|
|
宮武外骨にとって最も信頼できる部下だった三好米吉は、明治43年古書籍美術店”柳屋書店“を起こした。米吉が出版したユニークな雑誌が「美術と文芸」で「柳屋」はその後継誌である。宮武外骨の「滑稽新聞」に係わり、明治後期の大阪に出版の小さな火を灯しながら与謝野晶子・鉄幹等と交流した。近代大阪の出版史を三好米吉を中心にお話しいただきます。
|
|