としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2009年12月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 天文 |
2009年、世界天文年も終わりに近づいています。そこで、今回のテーマは、「天文」でお届けします。
広い宇宙の広がりを、この小さな「としょかんせんなりびょうたん」の中に感じていただけるでしょうか。
なお、当コーナーは、リニューアルを期して、しばらくの間、お休みをいただきます。
これまでのご愛読、ありがとうございました。
|
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 日・月・星 天文への祈りと武将のよそおい |
| 仙台市博物館編集 仙台市博物館 2004年10月刊 表紙天体写真:小石川正弘 |
 |
戦国時代、武将たちは神仏の加護を求めて、日・月・星をその装いにあしらいました。この資料は、有名な伊達政宗の半月をかたどった兜の前立を始めとして、さまざまな武将たちの装いがカラー写真で掲載された、仙台市博物館特別展の図録です。何気なく見ていると見過ごしてしまいそうな単純な文様にも、深い祈りが込められていることに気付かされます。
なお、この資料は現在絶版となっているそうです。貸出はできませんので、図書館館内でお楽しみください。
|
| |
| 都会で星空ウォッチング (Nature guide) |
| 小学館 2002年1月刊 |
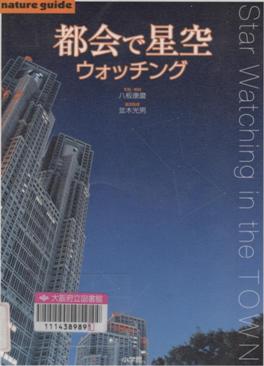 |
星空を観察するには、星のきれいなところへ出かけないといけないかというと、そうではありません。この本では、都会で星空観察を楽しむ方法が紹介されています。夜が明るい都会のほうが、明るい星だけが見えるため、星座を見つけやすいという利点もあるそうです。
例えば、写真ごとに「肉眼で見える星空」「双眼鏡を使うと見える星空」「望遠鏡を使うと見える星空」といった目安が表示され、また星についても「都会で見える」「郊外で見える」「美しい空で見える」と分かりやすく紹介されています。春夏秋冬の「都会の星座早見」も付録で付いています。
高層ビルと星座の競演も、またロマンチックです。普段の暮らしの中で、四季折々の星座観察を楽しんでみませんか。
|
| |
| 宇宙探検すばる望遠鏡 |
| 海部宣男監修 林左絵子文 新日本出版社 2005年5月刊 |
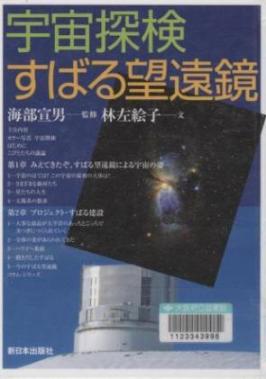 |
天体観測の研究になくてはならないもの、それは望遠鏡です。世界最大級のすばる望遠鏡は、大勢の人々の協力によって完成しました。その大きさは、宇宙からの光や赤外線を集める主反射鏡(主鏡)が直径8.2m、本体は高さ約22m、重さ約555tにもなります。主鏡にするためのガラスは、作り始めて7年、磨き始めてから3年もかかったそうです。もちろん大きさばかりではなく、高い観測性を誇ります。「世界に1つしか存在しない、超精密な重機械」、それが「すばる」なのです。
本体の仮組み立ては、大阪市此花区の日立造船桜島工場で行われ、その跡地は、現在ユニバーサル・スタジオ・ジャパンになっています。
あわせて『大望遠鏡「すばる」誕生物語 星空にかけた夢』(小平桂一著 金の星社 1999年12月刊)
を読んでいただければ、完成までの様子を更に詳しく知ることができます。また、『すばる望遠鏡 8.2m光学赤外線望遠鏡』(文部科学省国立天文台 c2003)もあります。
|
| |
| 宇宙 最新画像で見るそのすべて |
| ニコラス・チータム著 梶山あゆみ訳 河出書房新社 2009年7月刊 |
 |
人口衛星、惑星探査機、宇宙望遠鏡がとらえた最新の宇宙の姿が、200枚近いカラー写真で紹介されています。私たちの目では見ることができない波長の光を可視光に置き換えて画像にした結果、思わず見入ってしまうほどの美しい写真集になりました。
天の川銀河の中心やブラックホールなどの珍しい写真を楽しみながら、地球から始まり、太陽系、銀河系、マゼラン雲、そして宇宙の果てへと続く長い旅に出かけてみませんか?
|
| |
| プラネタリウムを作りました。 7畳間で生まれた410万の星 |
| 大平貴之著 エクスナレッジ 2003年6月刊 |
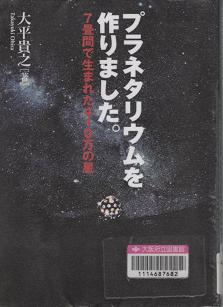 |
特に天文に関心の深くない方でも、コンサートやイベントなどで、著者の作った移動式プラネタリウムによる星空と出会っているかもしれません。
著者は、小学生時代、夜光塗料で自分の部屋に星空を作り、やがて大人になって、軽量で、しかもこれまでにないたくさんの星を投影することのできる、高性能な移動式プラネタリウムの製作に成功しました。
エンジニアだった隣の人が親切に手ほどきをしてくれたこと、科学館の職員が、プラネタリウムの裏側を見せてくれたこと、レンズメーカーの工場の人が「プラネタリウムを作りたいという事情を説明したら、何十枚かのレンズをただで」「見ず知らずの子供に分けてくれ」たこと、など、周囲の人が応援してくれた小学生のころの思い出や、自作プラネタリウムにまつわる逸話、略図や写真を多用してのエアドームやプラネタリウムの仕組み、さまざまなパーツ作りの説明が、親しみやすく書かれています。
|
| |
| 完全ガイド皆既日食 |
| 武部俊一著 朝日新聞出版 2009年5月刊 |
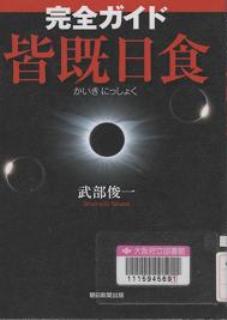 |
2009年7月22日、日本では46年ぶりに見ることができると予告された皆既日食。あいにく快晴には恵まれませんでしたが、大阪でも、普段の曇天とはかなり印象の違う、真っ暗な空を、多くの人が見上げました。今年の日食の「復習」、次回の日食の「予習」として、世界各地で撮影された日食の写真や、次の日食予定日、観測の注意や観測ツアーの紹介のほか、著者が収集した、日食をモチーフにした切手や、神話や史実に見る日食らしき出来事の解説、日食の出てくる映画など、日食にまつわることがらが、コンパクトな一冊にまとまった、この本はいかがでしょうか。
ほかに、日食を愛し、追い続ける人々の作った『皆既日食ハンターズガイド 』(STUDIO VOICE別冊 eclipseguide.net編 INFASパブリケーションズ 2006年2月刊)も所蔵しています。
|
| |
| 日本の星 星の方言集 |
| 野尻抱影[著] 中央公論社 1975年刊 |
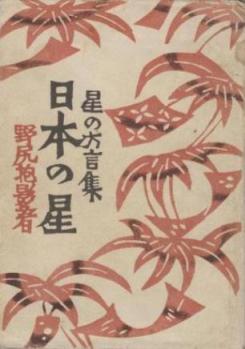 |
私たちは星の名前をどれくらい知っているでしょうか。
この本は、日本での星の呼び方にこだわり、文献を丹念に調べ、日本全国からも情報を集め、ときに手書きのカットもまじえてまとめあげられたものです。著者が「日本人の眼に映じたる星」(『南蛮更紗』(東洋文庫 596) 新村出著 平凡社 1995年12月刊に収録)という文章をきっかけに「星の和名」に関心を持ち、調査を進めていく過程について、はしがきに詳しく述べられています。
「鯖売り星」「平家星」「源氏星」・・・などなど、なるほど日本の名前だなあ、と感心する一方、今ではなじみの薄くなった農具「箕(み)」の名前などが出てきたりします。
少し難しい字が多いですが、装丁が美しく、中身も味わい深い本ですので、ぜひご覧ください。
著者の生い立ちや研究について詳しく知るには、
『野尻抱影 聞書“星の文人”伝』 (シリーズ民間日本学者 21 石田五郎著 リブロポート 1989年9月刊) 『学問と情熱 21世紀へ贈る人物伝 第22巻 野尻抱影』(紀伊国屋書店ビデオ評伝シリーズ 紀伊国屋書店(発行) [2002年5月刊] ビデオテープ) などがあります。
当館にはここで紹介した以外にもこの著者の、星に関する本や随筆を数多く所蔵しています。あわせてご覧ください。
|
| |
| 世界の太陽と月と星の民話 (世界民間文芸叢書 別巻) |
| 日本民話の会外国民話研究会編訳 三弥井書店 1997年6月刊 |
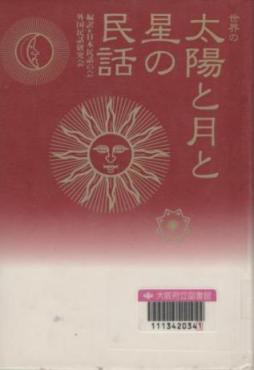 |
月の中にウサギがいてお餅つきをしていたり、七夕だけ天の川をわたることができたり、民話・伝説には天文に関わるおはなしがたくさんあります。この本には、時代や国の文化によって、天体の解釈も似ていたり、違っていたり、数ある世界の民話の中から、北はアラスカから南はアルゼンチンまで、世界各地63箇所123話の、太陽と、月と、星に関わるお話が収録されています。出版社によれば、現在品切れ中とのことですが、図書館で借りて読んでいただくことができます。
月の満ち欠けを各章のタイトルとして、月にまつわる古今東西の13のお話を集めた『月の光のなかで』
(キャロリン・マックヴィッカー・エドワーズ著 椎名葉訳 ぺんぎん書房 2004年3月刊)
も所蔵しています。
|
| |
| モマの火星探検記 |
| 毛利衛著 講談社 2009年10月刊 |
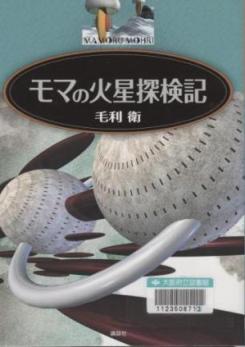 |
二度の宇宙飛行を果たした、毛利衛さんの初のSF小説です。
2033年、人類史上始めて火星に降り立った6人の宇宙飛行士たち。28歳のモマは、最年少乗組員として参加しています。火星へと向かう途中、最愛の息子ジュピターの死を知るホルストさん。その後、まるでホルストさんの哀しみとジュピターの魂を癒すかのように、不思議な出来事が次々と起こります。火星パセリや宇宙キャベツなどの宇宙野菜や、ロボット犬のタロー、シローなども登場し、読みながらわくわくさせられます。
著者の宇宙飛行士としての体験に裏づけされた的確な描写は、まさに宇宙文学と呼ぶにふさわしく、地球や、人間を含む生命への限りない愛おしさに満ち溢れた物語です。
|
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]