としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2009年7月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 図書館へようこそ! |
図書館ときいて、思い浮かべるイメージは十人十色。みなさまの「図書館」はどんなところですか?
当館作成の図書館サービス紹介パネル、「そんなとき、図書館へ」もぜひ一度、ごらんください。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 図書館に行ってくるよ シニア世代のライフワーク探し |
| 近江哲史著 日外アソシエーツ 2003年11月刊 |
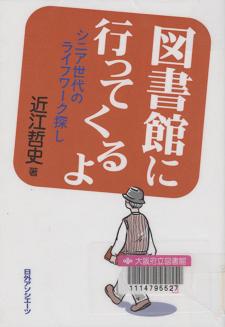 |
図書館って何をするところ? とたずねてみると、意外と百人百様の答えが返ってくるのかも知れません。読書家で学生時代からいろいろな図書館を利用してきたという著者が、「ひまつぶしに」「ものを調べに」「読書に」…と、いくつかの使い方を例に挙げながら、図書館についてあらゆることを語りつくした、利用者による、利用者のための図書館利用法の本です。
近所の市立図書館と大学図書館の使い分けや、司書の活用法、といった利用の秘訣から、今、図書館界で問題になっていること、などなど、語られる話題は尽きることがないようです。シニア世代に限らずどなたが読まれても、今よりもっと図書館の利用の幅が広がることでしょう。
|
| |
| まちの図書館でしらべる |
| 『まちの図書館でしらべる』編集委員会編 柏書房 2002年1月刊 |
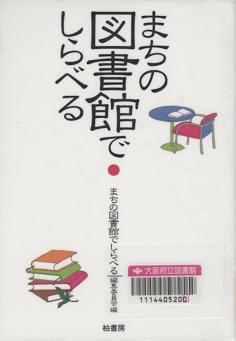 |
「もしかしたら、あなたはいままで『まちの図書館は無料で本を貸してくれるところ』というイメージしかもっておらず、何かしらべたいときに相談できるなんて思いもしなかったかもしれない。」(本書72〜73ページより)と、著者が心配しているように、資料の貸出ほどには知られていないようですが、図書館にとって、利用者のみなさまの調べ物のお手伝いをするのは大事な役割のひとつなのです。
第1章「図書館で謎を解く」では、そんなまちの図書館の奮闘ぶりが描かれます。取引先で聞いた「ユーロ1」とはどんなものか?アメリカの州は50じゃない?「鐘の鳴る丘」の主題歌の歌詞と楽譜が欲しい(注:主題歌のタイトルは意外や「鐘の鳴る丘」ではありません!)・・・。極めつけは「ミナミのサンショ」という有名なタイの小説が読みたい、というもの。タイの知人から聞いたというこのタイトルでは、いくら調べても分かりません。その真相は?
この本の登場人物のように、心の片隅にひっかかっている疑問や、仕事で、生活で知りたくなった事柄を、図書館で調べてみませんか?
この本以外にも図書館で調べものをするための本は多数出版されていますが、レポートや論文に頭を悩ませている学生さんには、『図書館に訊け!』(ちくま新書486 井上真琴著 筑摩書房 2004年8月刊)もお勧めです。「図書館の隠密」を志して大学図書館員になったという著者が、会得した「極私的、図書館利用テクニック」を伝授してくれます。
ビジネスマンの方には『図書館を使い倒す! ネットではできない資料探しの「技」と「コツ」』(新潮新書140 千野信浩著 新潮社 2005年10月刊)を。『週刊ダイヤモンド』の記者である著者が活用している情報源は「図書館」。その技とコツが惜しげなく披露されています。
|
| |
| 図書館って、どんなところなの? (図書館へいこう!1) |
| 赤木かん子文 すがわらけいこ絵 ポプラ社 2007年7月刊 |
 |
「調べ学習」と聞くと、夏休みの宿題というイメージがありますが、図書館では1年中いつでも調べ学習のお手伝いをしています。このシリーズの2『本って、どうやって探したらいいの?』(2007年8月刊)と3『テーマって・・・どうやってきめるの?』(2007年8月刊)も合わせて読めば、調べ学習が決して難しいものではなく、誰にでもすぐに始められるような気がしてきます。シリーズ3のあとがきでは、そもそも「調べ学習って、なんのためにするの?」という疑問に、著者の赤木かん子さんが明快に答えてくださっています。
この他にも、調べ学習についての本には『本のさがし方がわかる事典』(金中利和監修 造事務所編集・構成 PHP研究所 2007年11月刊) や、『図書館へ行こう!図書館クイズ』(山形県鶴岡市立朝暘第一小学校編 国土社 2007年3月刊)などがあります。
|
| |
| しずかに!ここはどうぶつのとしょかんです |
| ドン・フリーマン著 なかがわちひろ訳 BL出版 2008年4月刊 |
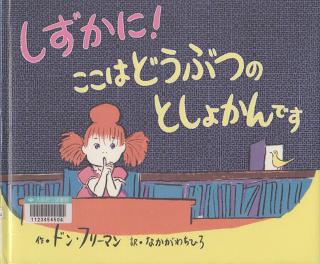 |
カリーナは図書館が大好きな女の子。土曜日の朝には、必ず図書館に行きます。「わたしがとしょかんのひとだったら、どうぶつだけがとしょかんにはいれるとくべつなひをつくるのに」。本を読んでいるうちに、想像がどんどん広がっていく読書の醍醐味は、大人も子どもも同じです。
また、図書館では静かにする、という決まりを守りさえすれば誰でも図書館を利用できます。たとえライオンでも!?
『としょかんライオン』(ミシェル・ヌードセンさく ケビン・ホークスえ 福本友美子やく 岩崎書店 2007年4月刊)
静かにできなかったおサルもいますね。
『おさるのジョージとしょかんへいく』(M.レイ原作 H.A.レイ原作 福本友美子訳 マーサ・ウェストン画 岩波書店 2006年4月刊)
2009年7月現在、予約が多数ついていますが、『図書館ねこデューイ 町を幸せにしたトラねこの物語』(ヴィッキー・マイロン著 羽田詩津子訳 早川書房 2008年10月刊)は、図書館と動物をテーマにした大人向けのノンフィクションです。
|
| |
| 図書館の誕生 ドキュメント・日野市立図書館の20年 |
| 関千枝子著 日本図書館協会 1986年4月刊 |
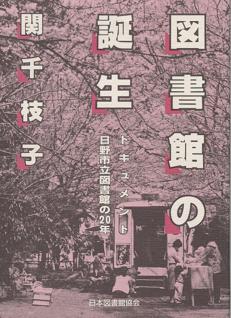 |
その昔、日本の図書館はどことなく薄暗く、時には寄りつきがたいイメージがあるところでした。「日本人は本を買うのが好きだから、図書館では借りない」などという俗説もあったといいます。
それが大きく変わったのは、日野市立図書館の誕生と成功によってでした。
1965年以降、日野市立図書館は、館内閲覧中心のそれまでの考え方を変え、本の貸出を中心的なサービスとし、そのために、まず移動図書館車で市民のもとに出向き、次に市内各所に小さな分館をたくさん建てました。図書館にない本はすぐ取り寄せる「予約」を始め、利用者本位のサービスを徹底したことで、大勢の市民でにぎわうようになりました。
すべての人に親しまれる「市民の図書館」はこの時、誕生したのです。様々な困難に直面してもその都度乗り越え、「本当の図書館」をつくろうとした図書館員たちの姿を追ったドキュメントです。
|
| |
| バスラの図書館員 イラクで本当にあった話 |
| ジャネット・ウィンター絵と文 長田弘訳 晶文社 2006年4月刊 |
 |
この絵本のカバーのあらすじ紹介には、「図書館の本には、私たちの歴史が全部つまっている」とかかれています。戦争が始まり、いよいよ爆撃の危険がせまったとき、図書館員のアリアさんがしたことは・・・。
ほかに、戦争や災害で図書館や図書館資料が危機にさらされたり、実際に失われてしまったりした歴史を伝える資料としては、
『図書館の興亡 古代アレクサンドリアから現代まで』 (マシュー・バトルズ著 白須英子訳 草思社 2004年11月刊)
『略奪した文化 戦争と図書』(松本剛著 岩波書店 1993年5月刊)
『戦争と図書館 (昭和史の発掘)』(清水正三編 白石書店 1977年2月刊)
失われた文化を再び取り戻そうと始まり、広がる図書館活動を伝える資料としては、
『図書館への道 ビルマ難民キャンプでの1095日』 (渡辺有理子著 鈴木出版 2006年1月刊) などがあります。
|
| |
| 図書館革命 |
| 有川浩著 徒花スクモイラスト メディアワークス 2007年11月刊 |
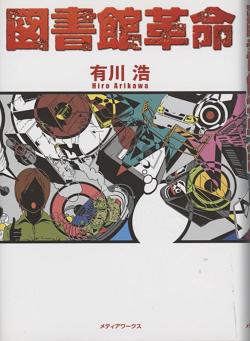 |
漫画やアニメにもなり、2008年にはシリーズとして第39回星雲賞日本長編作品部門を受賞した「図書館戦争」4部作の完結編。当館では2009年7月現在予約多数。DVD『図書館戦争』1 2 3
も人気です。
作品中の「図書館の自由に関する宣言」は、同名の宣言が実在しますが、一部文言が違います。元ネタの詳細は、ウェブでは日本図書館協会ホームページの「図書館の自由に関する宣言」、図書では四ヶ国語版の『図書館の自由に関する宣言1979年改訂-日韓中英』(日本図書館協会図書館の自由委員会編 日本図書館協会 2006年8月刊 )などで読むことができます。
なぜそんな宣言を作ったの? と興味をもたれた方は、『図書館の自由に関する宣言の成立』(日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員会編 図書館と自由 第1集日本図書館協会 1975年刊)をどうぞ。2004年には復刻版 も刊行されました。
このほか、図書館の自由をテーマにした小説では、アメリカの学校図書館で『ハックルベリー・フィンの冒険』が問題になる『誰だ ハックにいちゃもんつけるのは』(ナット・ヘントフ[著] 坂崎麻子訳 集英社文庫 コバルト・シリーズ 集英社 1986年1月刊)、
事例集『アメリカで裁かれた本 公立学校と図書館における本を読む自由』 (上田伸治著 大学教育出版 2008年7月刊)では、近年の、ハリー・ポッターやシェイクスピア作品などを読む権利をめぐる裁判事例が9つ、挙げられています。
|
| |
| 図書館戦隊ビブリオン (コバルト文庫) |
| 小松由加子著 集英社 1998年7月刊 |
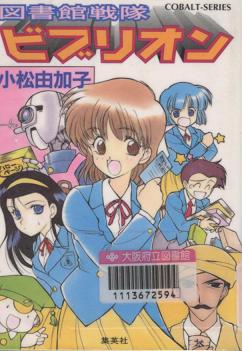 |
『図書館戦争』をさかのぼること約8年。図書館活劇小説はすでに現れていたのでした。
図書委員になった一年生4名を待ち受けていたのは、図書委員長の牧村レオナルドと、巨大化した紙魚(しみ。書物や衣類を食べる小さな昆虫。)が巣食う書庫。図書館の星から来た不思議な紳士と本の妖精に導かれ、ビブリオンパワーを得た委員長と4人は、図書館をおびやかす悪の組織を迎え撃つ・・・。
戦隊とは言っても、武器や激しい戦闘シーンはありません。ビブリオンは、見たいテレビ番組や予備校の時間を気にしたり、何とかカウンター当番をサボろうなどと思いつつ、突然ごちゃごちゃとわいて出る悪の組織の手先と、がまんくらべのような、とんちくらべのようなほのぼのした攻防を繰り広げるのです。
この物語では、図書館では当たり前に使われる言葉、例えば「閲覧」「利用者登録」「可動式書架」「分類番号」などをさりげなく話の展開に取り入れ、図書館のことをよく知っている人もそうでない人も楽しく読めます。
また、続編の『図書館戦隊ビブリオン2』では、悪の組織の四天王の正体が明らかに。
|
| |
| ファンタージエン 秘密の図書館 |
| ラルフ・イーザウ著 酒寄進一訳 ソフトバンククリエイティブ 2005年10月刊 |
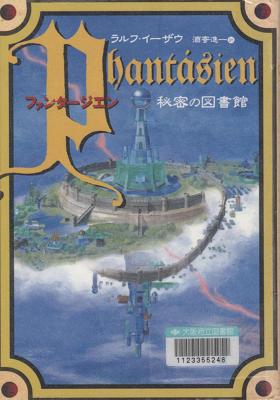 |
人の想像力と深く結びついた内なる世界ファンタージエンと、現実の世界である外国(とつくに)との間にあり、書かれなかった本、失われた本までも所蔵する秘密の図書館、ファンタージエン図書館。
本を愛し、ちょっと自分に自信の無い青年コレアンダーは、次々に図書館から姿を消す本の謎を追って探索に旅立ちます。彼はちょっとした失敗をしては「ぼくには無理だ」と弱気になってしまいますが、仲間の励ましや明るさに助けられ、一つ一つ課題を乗り越え、ファンタージエンを危機にさらしているたくらみに勇敢に立ち向かいます。
ファンタージエンとは、ドイツの作家ミヒャエル・エンデの長編『はてしない物語』(岩波書店 1982年6月刊 )の舞台として登場する世界です。同作品は映画化もされているので、そちらを思い出される人もいるでしょう。→『ネバーエンディング・ストーリー』
『ネバーエンディング・ストーリー 第2章』
この『ファンタージエン 秘密の図書館』は、『はてしない物語』に着想を得て新たに創作されたものです。そのため、この作品は一つの完結した物語でありながら、私たちがまだ知らなかったファンタージエンの物語の一部でもあります。面白い本を読んでいる時だけに味わえる独特の緊張感、幸福感とともに、自分の心に描いていたファンタージエンの景色がなつかしさとともによみがえってきます。
なお、『ファンタージエン』はドイツの作家陣によって連作されており、あと5作品があります。ファンタージエンの世界に興味を持たれたら、ぜひお読みください。
『ファンタージエン 愚者の王』 ターニャ・キンケル著 ソフトバンククリエイティブ 2006年3月刊
『ファンタージエン 忘れられた夢の都』 ペーター・フロイント著 ソフトバンククリエイティブ 2006年10月刊
『ファンタージエン 夜の魂』 ウルリケ・シュヴァイケルト著 ソフトバンククリエイティブ 2007年3月刊
『ファンタージエン 言の葉の君』 ペーター・デンプフ著 ソフトバンククリエイティブ 2007年10月刊
『ファンタージエン 反逆の天使』 ヴォルフラム・フライシュハウアー著 ソフトバンククリエイティブ 2008年3月刊
|
| |
| 映画の中の本屋と図書館 |
| 飯島朋子著 日本図書刊行会 2004年10月刊 |
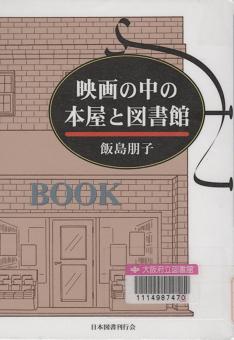 |
この本は、『図書館の学校』という雑誌(現在の誌名は『あうる』)に、「本・本屋・図書館 in Cinema」という題名で連載されたコラムをまとめたものです。
書名のとおり、本屋さんと図書館が登場する映画を紹介していますが、驚くのは視点の細かさです。新聞を閲覧する場面、閉館間際の場面、小学校の図書室、高校の図書室・・・などなど、実に多様な場面や場所を切り口に、たくさんの映画が紹介されています。
この本で取り上げられている映画の中には、当館でビデオまたはDVDを所蔵しているもの、原作本を所蔵しているものもあります。ぜひ参考にしていただければと思います。
続編として『映画の中の本屋と図書館 後篇』もあり、とくにメディアの中での図書館のイメージを研究する材料という観点から「図書館映画に関する文献の紹介」が収録されています。
|
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]