としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2008年9月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 防災・サバイバル |
| 防災の日・9月1日にちなみ今回のテーマは「防災」、ちょっと広げて「サバイバル」。危険を回避し、生き残るためのお役に立てば幸いです。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 学校防災マニュアル 改訂版 |
| 兵庫県教育委員会 2006年3月刊 |
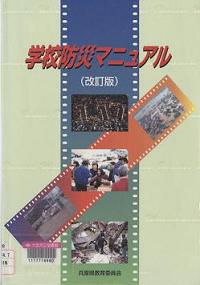 |
タイトル通り学校現場を対象とした資料ですが、私たちの生活にも参考になる情報がまとめられています。「第1章 日常における安全対策」では、設備・備品などの転倒防止の具体例やチェックポイントが紹介されています。阪神大震災の体験を踏まえての「第5章 心のケア」や、「資料編」の「防災教育の実践に役立つホームページ集」なども興味深いです。地震のみならず、今後想定される様々な自然災害から生き延びるために、お役立てください。
|
| |
| 緊急時の応急手当と事故防止 応急手当普及ビデオ (DVD) |
| マスターワークス(制作) 2007年刊 |
 |
現在、AED(自動体外式除細動器)は、医療従事者だけでなく、一般の人も利用できる心肺停止時の有効な医療機器として、当館を含め、公共機関などで広く設置が進められています。
このDVDには、AEDの操作を含め、心肺が停止したときや、気道に異物が入って 呼吸が出来なくなったときのための応急手当について、乳児、小児、成人とそれぞれの対応が収められています。
「大切な人が倒れてしまったら」と考えると、DVDを見るだけでは心もとないかもしれません。でも見ると「何かできるかも」と思えるかもしれません。ぜひお試しください。
|
| |
| 虫を食べる人びと |
| 三橋淳編著 平凡社 1997年6月刊 |
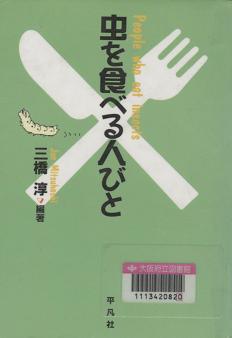 |
食糧難がきたときに何を食べるか。
世界の人口増加が懸念される中、昆虫は、新しい動物性タンパク資源として注目されているそうです。実は、最初に人類が出現した頃のヒトの主食は昆虫だったとのこと。
「昆虫はいわゆる救荒食あるいはサバイバル・フードとしても重要である」と、著者は主張します。
昆虫食というと、テレビなどで紹介される、いわゆるイカモノ食いが印象にありますが、本著では、イカモノ食いは原則として取り上げず、世界各地での昆虫食の歴史・食べ方・栄養を紹介しています。
昆虫食については、他にも『昆虫食はいかが?』(ヴィンセント・M・ホールト著 青土社 1996年8月刊)や『虫の味』(篠永哲・林晃史著 八坂書房 1996年10月刊)などがありますが、昆虫を食べるのはちょっと・・・と思われる方は、山野草や野生植物を食べるための本はいかがでしょう。
『山野草を食べる本 食べられる山野草132種・きのこ30種』(講談社編 1990年4月刊)
『食べられる野生植物大事典』(橋本郁三著 柏書房 2003年7月刊)
『おばあちゃんの山野草 これがおいしいベスト100』(本田力尾著 主婦の友社 1988年3月刊)などがあり、
また、子供向けにも『道ばたの食べられる山野草』(村田信義 写真と文 偕成社 1997年6月刊)もあります。
読んでいると、本当においしそうで、サバイバルな状況ではなくても、山野草を味わってみたくなりますよ。
|
| |
| イラスト図解十五少年漂流記 |
| J.ベルヌ原作 PHP研究所編 PHP研究所 2007年8月刊 |
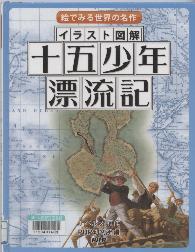 |
寄宿学校の少年たちを乗せた船は、夜の間に外洋に出てしまい、翌朝乗船してくるはずだった船長はじめ大人が不在のまま、嵐に流されて無人島へ。15人の少年たちは助け合って生き延び、やがて・・・・。日本ではたくさんの翻訳も出されて親しまれたこの作品を、時代背景や少年たちが使ったと想定される当時の道具なども含めて、イラストで解説するのが本書です。もう一度、物語を読んでみたくなった方には、当館所蔵分の中でも1968年刊の完訳版「二年間の休暇」(J・ベルヌ作 朝倉剛訳 太田大八イラストレーション 福音館古典童話シリーズ 1 福音館書店) が、40年前の刊行ながら、丁寧に読まれ、きれいに保存されているのでお勧めです。(翻案、抄訳も所蔵しています。)
さて、日本には、近海の孤島に漂着して、人生の半分を過ごした人々の記録が残っています。「鳥島漂着物語」(小林郁著 成山堂書店 2003年刊)
では、多くの記録や実地調査によって、江戸時代中期に、アホウドリの生息する無人島「鳥島」(別名伊豆鳥島:東京から約580キロ南の太平洋上、八丈島と小笠原諸島とのほぼ中間に現在もある無人島)に流れ着いた人々がどのように生き抜いて生還したか、そのサバイバル生活について、考証されています。
絵本もあります。
「アホウドリの島 鳥島漂着ものがたり」(川村たかし著 武部本一郎絵 絵本ノンフィクション 5 岩崎書店 1977年刊) |
| |
| 釣り人の「マジで死ぬかと思った」体験談 |
| つり人社出版部編 つり人社 2004年7月刊 |
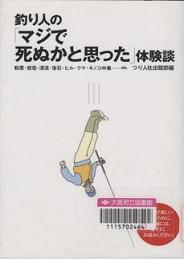 |
この本では、月刊「つり人」に連載されたものを基本に、22のエピソードが、「マジで死ぬかと思った度」を★の数で判定しながら掲載されています。だいたい★2つから4つ、しかし中には「測定不能」とされた感電例も!!釣りに出かける前に目を通しておけば、無用の危険は避けられるかもしれません。死にそうな目にあってもそれでやめたという例はなく、釣りの魅力のおそろしさが思いやられます。
シリーズは現在3巻まで発行されています。
|
| |
| 雑草たちの陣取り合戦 身近な自然のしくみをときあかす |
| 根本正之著 小峰書店 2004年11月刊 |
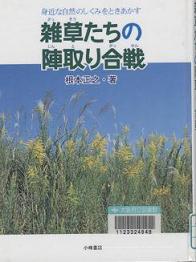 |
植物の世界にも熾烈な生存競争があります。本書では光と水を奪い合い、繁殖力の強いものだけが生き残れる雑草社会のさまざまな暮らしを紹介しています。たとえば、シバやセイタカアワダチソウは地下茎から攻撃をしかけ、陣地を広げていきます。遠くの陣地に潜りこむのであれば、種子が散布できるヤマノイモやタンポポが有利です。オオバコやツユクサなどは隙間を狙って共存できる得意技で生き延びようとします。普段はほとんど見向きもされない雑草たちですが、懸命に生きる姿と強靭な生命力には驚嘆するばかりです。
関連本として、心地よい文体とリアルな絵で荒れ畑に生存する雑草の四季を絵本にした『雑草のくらし あき地の五年間』(甲斐信枝さく 福音館書店 1985年4月刊)
生き残るために形態を進化させた植物を豊富な写真で紹介した『世界の不思議な植物 厳しい環境で生きる』(湯浅浩史著 誠文堂新光社 2008年2月刊)
があります。あわせてご覧ください。
|
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]