としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2008年4月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| サクラサク お花見の本 |
寒かった冬も終わり、いよいよ春がやってきました。大阪でも3月26日に桜の開花が報じられて、お花見の準備をしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今月はお花見に関する本を集めてみました。お花見というと桜と考えられるかと思いますが、今回はほんの少しだけ広く集めてみました。
本物のお花見の前に図書館でのお花見はいかがでしょうか。
(……ただし、他の方のご迷惑となりますので、図書館内で本当に宴会をするのはご遠慮ください……)
|
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| SAKURA |
| 森田敏隆 著 世界文化社 2005年3月刊行 |
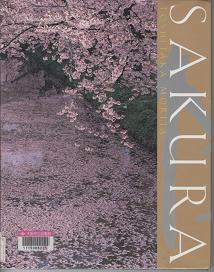 |
世の中にあまたの花はあるけれど、日本で春のお花見といえば、やはり一番人気は「桜」。マスコミでも、駅の窓口でも、天気予報でも、桜の開花状況が報道される人気ぶりです。
たくさんある桜の写真集の中から、今回ご紹介するこの本では、桜の花木・風景の写真だけでなく、「桜襲(さくらがさね)」、「花見(はなみ)」、「花守(はなもり)」といった関連の事柄についても解説しています。
本文と掲載写真説明はすべて英文併記です。
以下の本もあわせてご覧ください。
『一本桜百めぐり 森田敏隆写真集』 森田敏隆著 講談社 2004年2月刊
|
| |
| さくら 月刊かがくのとも2005年4月号 |
| 長谷川摂子著 矢間芳子絵・構成 福音館書店 |
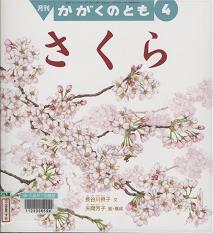 |
桜は、一年に一度だけ、しかもほんの短い期間だけ、美しい花の景色を私達の心に焼き付けて散っていきます。
しかし花の後にも、桜の生命の営みは続いていくのです。葉桜になったかと思うと、葉陰に小さなサクランボ、夏には虫でおおにぎわい…そして次の美しい花の命を抱いて、寒い冬を越えていきます。
桜の木の一年のドラマが、長年の観察にもとづく精緻な絵とリズム感のある文章によって描かれ、くりかえされる生命の営みと輝きを感動的に伝えます。
|
| |
| 通り抜け その歩みと桜 |
| 造幣局泉友会編 創元社 1996年4月刊 |
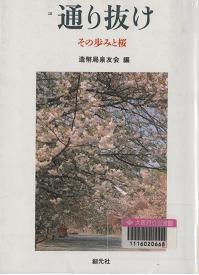 |
大阪の春の風物詩である造幣局の桜の通り抜けが始まったのは、明治16年のこと。毎年、4月の中旬には、約124品種、約370本の桜が見ごろを迎えます。
本書は100年以上の歴史のある通り抜けの歩みを桜の写真と共に紹介しています。高度成長期には、大気汚染の影響により、桜が枯死してピンチを迎えたり、花見客に桜の枝を折られたり、死傷者が出た年もあり、心配や苦労も多いようです。自然破壊や安全に気を配りながら、お花見を楽しんでもらえればと願います。
桜の通り抜けについては、以下の本もありますので、ご覧ください。
『通り抜けの八重桜 カラーアルバム』 造幣局泉友会 1993年刊
『通り抜けの桜』 忍泰男著 創元社 1989年刊
|
| |
| さくら 日本の美2 |
| 鈴木進監修 小松大秀[ほか]執筆 美術年鑑社 2001年3月刊 |
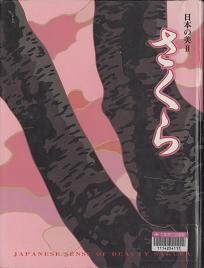 |
桜は古来より親しまれ、絵画や図案、和歌や物語などで取り上げられてきました。
そこには実物の桜にはないまた別の美しさがあります。
本書は平安時代の絵巻から現代の作家まで、桜をモチーフにした絵画・絵巻・蒔絵などを集めています。
これを機会に桜と人々をめぐる歴史と美に触れてみてはいかがでしょうか。
桜に限らず、花と日本の文化との関わりについてさらにお知りになりたい方は以下の本もご覧ください。
『花の変奏 花と日本文化』 中西進・辻惟雄編著 ぺりかん社 1997年3月刊
『日本の図像 花鳥の意匠』 ピエ・ブックス 2007年9月刊
|
| |
| 襖絵の梅に蝶がとまる 直原玉青(じきはらぎょくせい)水墨画の世界 (ビデオ) |
| 静岡放送(製作) 19- |
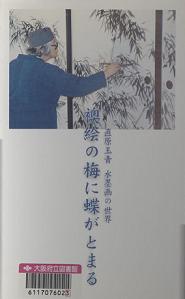 |
このビデオではまず、直原玉青氏が水墨画を描いていく光景に圧倒されます。真っ白な襖に、直原氏の筆先からあっという間に松や梅が描かれ、その梅の花に蝶の止まる様子までカメラに収められています。
直原氏は現代南画(水墨画)の第一人者で、映像でも「自然と対話して、一つの自然を創る」という言葉があります。白黒だけの単純な線で蝶が止まるほどの自然を生み出すために、どれほど花や木を見て自分の中で育てたかに想いを馳せずにはいられなくなります。
画家の目を通した花を見ると、お花見のあと自分の中に残る花も気になるかもしれません。ぜひお試しください。
|
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]