としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2008年1月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| お酒の本 |
| 平成20年がスタートしました。今月のひょうたんの中身はお酒です。新しい年を祝って「お酒の本」で乾杯〜!今年も「せんなりびょうたん」をよろしくお願いいたします。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 酒は飲め飲め 酒がすすむ民謡ベスト (CD) |
| 大塚文雄[ほか]唄 King Record 2007年3月 |
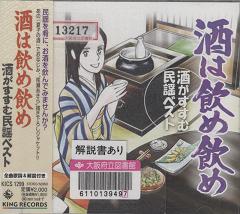 |
これは、お酒に関する民謡を収録したCDです。民謡に普段親しまれない方には、これを聴いても、副題のようにすぐ「酒がすすむ」という訳にはいかないかもしれません。ただ聴いていると、先人たちがお酒に臨んだ姿勢のようなものが、何となく伝わってくる気がします。
「酒はのめのめ」で始まる黒田節では、日本一の名槍を飲み取った黒田藩士の心意気。「仕事に楽はありゃしないヤラヨーイ」の酒屋【モト】摺唄では、酒母のもと摺りという酒造りの核心の仕事に取り組む厳しさ。それぞれどの唄からもお酒への様々な想いが、民謡ならではの明るくせつないリズムと節でじんわりとしみ込んで来ます。
これを聴くと、先人のお酒への思い入れを自らも飲んで確かめたくなるかもしれません。ぜひお試し下さい。(やっぱりお酒がすすむCDなのでしょうか) |
| |
| どうしてお酒飲むの? 月刊たくさんのふしぎ第204号 |
| 森枝卓士 著 古谷三敏 絵 福音館書店 2002年3月刊 |
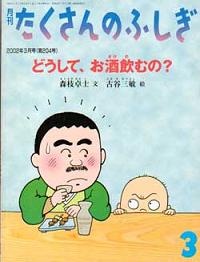 |
小学生、100人に聞きました。「大人のすることでいちばん不思議なことは?」第3位は「タバコを吸うこと」、第2位は「勉強、勉強とすぐ怒ること」、さて、輝く第1位は・・・「どうして大人はお酒を飲むの?」でした。
この本では、そんな子ども達の疑問を受けて、そもそもお酒とは何なのか、子どもがなぜお酒を飲んではいけないのか、どうしてお酒を飲むとお行儀が悪くなるのかなど、様々な角度から子どもの「なぜ?」にせまります。
バー「レモン・ハート」のオーナーで、お酒をテーマにした同名の漫画も描いている古谷さんの絵が親しみやすく、子ども達にも気軽に手にとってもらえそうです。
忘年会が終わったと思ったら、新年会など、お酒を飲む機会の多くなるこの季節・・・大人にとっては嬉しいやら、苦しいやらですが、そんな大人達を、子ども達は案外冷静に見ているようです。飲酒運転などの命に関わる事故もおこっています。なぜお酒を飲むのか、実は大人にもわかっていないのかもしれません。お酒のことが不思議な子どもはもちろんですが、大人のあなたもご覧になってみませんか? |
| |
| 日本の酒文化総合辞典 |
| 荻生待也編著 柏書房 2005年11月刊 |
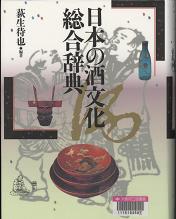 |
この本は、お米のお酒を中心に、お酒に関わることばを6200項目収録した辞典です。お酒そのものは苦手な方でも、例えば今の季節なら、「正月酒」「屠蘇」などのことばの定義を覗いてみてはいかがでしょう。参考図書ですので館内利用のみ可能です。図書館内でごらんください。
貸出できるものでは、お酒を十分味わいたい方にお勧めの
『「知識ゼロからの」日本酒入門』、
飲んだいいわけ、飲まない理由に引用できそうな言葉がいっぱいの
『日本の粋を伝えることわざ ことばの民俗学 6』、
お酒のいれものにまつわる、
『酒と器のはなし』、
『とっくりのがんばり―貧乏徳利は呑ん兵衛の味方』、
昔の人はどんな風にお酒を作り、楽しんでいたのか、
『日本酒の起源 カビ・麹・酒の系譜』、
ほか、さまざまな切り口で書かれた日本の酒文化の本があります。
|
| |
| 吟醸酒を創った男 「百試千改」の記録 |
| 池田明子著 時事通信社 2001年5月刊 |
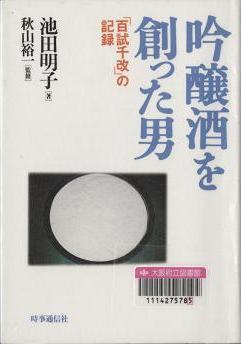 |
吟醸酒は米を精米のときに通常よりも多く削り、低温で長時間醗酵して作られたもので日本酒の中でも高級で人気があります。
この「吟醸酒」が作られはじめたのは実は明治になってからで、一般に飲まれるようになったのは第二次世界大戦後のここ30年ほどなのだそうです。
本書は、その誕生に大きく貢献した、広島の酒造家三浦仙三郎の歩みを紹介しています。酒造りをする人を取り上げた本ということで、職人の手わざに着目したものを想像されるかもしれませんが、三浦氏は温度を測定し、実験を繰り返すという科学的な方法でより品質の高いお酒を安定的に作ろうとしています。
おいしいお酒を飲む前に、それが生まれるまでの歴史を知ってみるのはいかがでしょうか?
吟醸酒の歴史については以下の本もあります。
『吟醸酒誕生 頂点に挑んだ男たち』、
『吟醸酒の来た道 至高の味わいを生んだ究極の技』、
とりあえず吟醸酒が飲みたい方は
『日本の大吟醸一〇〇』、
(情報が若干古いのでご注意を) |
| |
| 灘の酒つくり 文化財資料第37集 |
| 灘酒酒造用具調査団編集 西宮市教育委員会 1992年3月刊 |
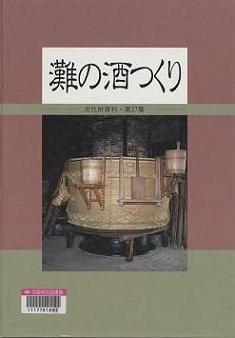 |
灘の酒は、全国的に有名でおよそ400年の歴史があります。
現在は、環境省の「かおり100選」に選定されている灘五郷(西宮市の今津郷、西宮郷、神戸市の魚崎郷、御影郷、西郷)で、ハイテク技術を駆使して、お酒が製造されています。
本書は、酒文化の歴史を後世に伝えるために伝統的な製造工程や道具を紹介した本です。実測図付き用具の解説や戦前の杜氏の風習、樽の作り方など民俗学的にも価値のある資料が満載です。
日本の伝統的な酒造りについてさらにお知りになりたい方は、
『酒つくりの匠たち』、
『杜氏千年の知恵』、
もご覧ください。
|
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]