としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2007年11月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 「収穫の秋」の本 |
| 今年は(も?)季節がどうも不順で、まだそれほど寒さはありませんが、やはり秋は秋。図書館の中からいろいろな「秋」を収穫してみました。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 日本どんぐり大図鑑 |
| 徳永桂子著 北岡明彦監修・解説 偕成社 2004年3月刊 |
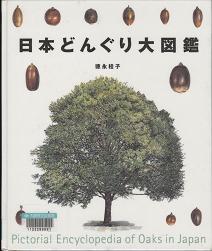 |
どんぐりが転がる季節となりました。当館をとりまく公園にも、たくさんのどんぐりが、ころころころ。丸いの、長いの、はかまのついたの、色も形もいろいろです。この、どんぐりたち、いったい、どこからきたのでしょう?
この図鑑では、実と葉が実物と同じ大きさで拾ったどんぐりと並べて比べることができるところがわかりやすく、日本で多く見られる40種類のどんぐりを、ルビつきで紹介しています。巻末には「どんぐり」とその周辺のお話や、用語解説と、英文の短い解説もついていて、大人にも子供にもわかりやすい一冊です。
|
| |
| きんいろのとき |
| アルビン・トレッセルト著 ロジャー・デュボアザン絵 江国香織訳 ほるぷ出版 1999年9月刊 |
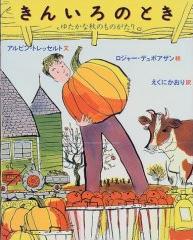 |
きりぎりすが鳴きはじめると、「霜がおりるまであと6週間」といわれます。こんな古い言い伝えが、秋の訪れを知らせてくれるのです。秋はめぐみの季節。森にも街に農場にも、収穫の季節がやってきます。
落ち葉が舞い、それを踏みしめて歩く学校からの帰り道。果実の収穫をお手伝いし、冷たくなってきた空気の中で、そっと息をつきながら星空を眺める・・
秋のはじまりから、感謝祭までの、農村の実り豊かな秋が描かれています。ページを繰ると、まばゆいばかりの黄色やオレンジの鮮やかな色彩が画面にあふれ、絵本を持つ手まで秋色に染まりそうです。美しい季節のうつろいを味わう喜びにあふれた絵本です。
季節感の少ない都会に暮らす子ども達に、こんな風に季節がめぐっていくことを、その豊かさと美しさのなかに少しでも感じてもらえたらと思います。 |
| |
| だれでもつくれる永田野菜 全10巻 (DVD)(書名の部分をクリックすると第4巻の書誌詳細画面にジャンプします) |
| だれでもつくれる永田野菜製作委員会(発行) 2006年1月刊 |
 |
これは野菜の作り方のDVDです。野菜作りが全く初めての方でも、したくても場所が、という方でも大丈夫。第1巻「準備編」では初心者の方から、第10巻「プランター編・全国永田農法産地巡りの旅」では「ベランダなら」という方まで幅広く対応しています。「自分で実りを育んでみたい」とつい思ってしまうDVDです。
それから『おいしさのつくり方−永田農法を家庭菜園で−』(諏訪雄一著 小学館 2006.2刊)は、このDVDを制作したプロデューサーが自ら野菜作りを実践した「使える本」です。合わせてどうぞ。
|
| |
| イノシシ農作物被害防止対策の手引き<事例集> |
| 滋賀県農政水産部農産流通課 2004年3月刊 |
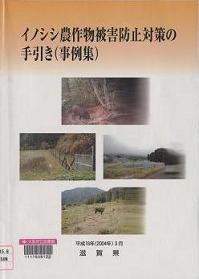 |
実りの秋!食べ物のおいしい季節です。しかし・・・農村では収穫の時期に精魂込めて作った農作物を野生動物に食い荒される被害が年々増大しています。
本書は日本各地のイノシシによる農作物被害防止対策の取組事例を基に農作物被害を軽減するための手法がまとめられています。
イノシシ以外にも滋賀県のHPではニホンザル、ニホンジカの被害防止対策の手引きも見ることができます。
「ニホンジカ農作物被害防止対策の手引き<事例集>」は近日受入れ予定(平成17年11月9日現在)です。
おいしい食べ物の裏側には、人と野生動物の生活をかけた回避できない闘いがあります。
これを機会に被害の因果関係となっている生態系のバランスや自然破壊についても考えてみませんか。
|
| |
| 飛行蜘蛛 |
| 錦 三郎著 丸ノ内出版 1972年4月刊 |
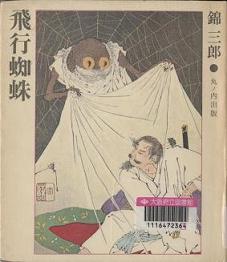 |
11月、山の上のほうが白くなり、そろそろ平地でも雪が降り出そうかというころ、山形県米沢盆地では、空を白く細い糸が舞います。人々はこれを「雪迎え」と呼び、冬支度を始めます。
この空飛ぶ白い糸、正体はクモが移動するために糸を出し、凧のように風を受けて空を飛ぶ姿でした。これは実は米沢盆地だけの現象ではなく、世界中で見られるものです。
本書では著者の長年の観察によりその正体やクモの種類などを特定し、また、国内外の研究成果や文学作品の中に出てくる「雪迎え」に似た現象なども紹介しています。
読み終えたあと、ふと空を見上げてみたくなる本です。 |
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]