としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2007年10月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 「通信」 伝えたいことは・・・? |
| 10月9日は世界郵便DAY、10月23日は電信電話記念日です。今回はそれらにちなんで「通信」に関連する資料を選んでみました。「通信」の漢字起源は”通い合って信頼を深めること”だそうです。皆さんの心に残るような資料がご紹介できているでしょうか・・・ |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 教科書には載らないニッポンのインターネットの歴史教科書 |
| ばるぼら著 翔泳社 2005年5月刊 |
 |
インターネットが誕生して、人々のコミュニケーションは大きく変わりました。
この本は、タイトルどおりインターネットが日本に入ってから2004年ぐらいまでの「歴史」について書かれたものです。ただ、それは技術発達史やネット産業史としての歴史ではなく、有名無名の人々がつくりだし、そして消えていったさまざまなHPやネット内で起こったさまざまな出来事や「事件」など、個人個人の営みの積み重ねでつくられてきたインターネットという文化の「歴史」として書かれています。
膨大な記述や詳細な年表、当時活躍していた人々のインタビューなどで構成されており、頻出するHP名やハンドル名などの固有名詞に最初はとまどうかもしれませんが、分からなくても読み進めますのでぜひ挑戦してみてください。 |
| |
| 知っておきたい地上デジタル放送 |
| NHK受信技術センター編 日本放送出版協会 2003年3月刊 |
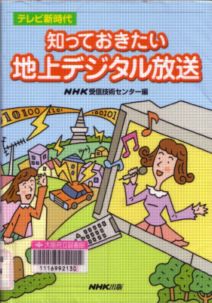 |
日本でテレビ放送が開始されてから半世紀が経ちます。私たちの暮らしに身近なテレビもアナログ放送からデジタル放送に切り替わり、2011年7月24日までにはアナログ放送が終了します。
デジタル放送は鮮明な画像が楽しめるだけでなく、過密になっている周波数が有効利用できるほか、 字幕放送やデータ放送(気象情報や交通情報など、生活に役立つ便利な情報をいつでも見ることができる)の多様なサービスを受けることが可能になります。
この本を読めば、受信方法や技術的な仕組みなどについても知ることができます。そろそろデジタル放送に切り替えようかとお考えの方は参考にされてはいかがでしょうか。 |
| |
| 旗振り山 |
| 柴田昭彦著 ナカニシヤ出版 2006年5月刊 |
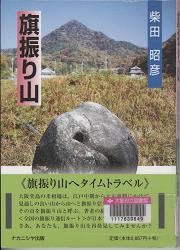 |
この本では、江戸中期から大正前期にかけて、峰から峰の見渡せる山に登り、旗を振って、大阪の米相場情報を全国に伝えた「旗振り通信」と、その拠点となった「旗振り山」が紹介されています。
昭和後半の実験では、高層ビルやスモッグに阻まれて、2時間20分かかった大阪ー岡山間も、昔はたった15分で通信できたという、驚きの早さの理由、旗が見えない天気の悪い日や夜の通信方法、情報が盗まれないように信号を変える工夫などにも触れられています。
各旗振り山の解説には、著者が実際に登ったときのコースガイドもついています。 |
| |
| 寺山修司&谷川俊太郎ビデオ・レター (ビデオ) |
| 寺山修司 谷山俊太郎出演 アートデイズ 1993年刊 |
 |
このビデオは、寺山修司と谷川俊太郎の往復書簡です。寺山さんが亡くなり、最後の16通目は宛先のない手紙になりました。
谷川さんは亡くなった友に「自分が誰かってことは、行為のうちにしか現れてこないような気がする」と語りかけます。
「もっと寺山の芯に近づきたかった」と悔やむ谷川さんですが、「私」というものを生涯にわたって疑ってきた寺山さんへの、優しい解答にも思えました。
見る人がそれぞれの見方を楽しめるビデオレターです。 |
| |
| トゥートとパドル ふたりのすてきな12か月 |
| ホリー・ホビー著 BL出版 1999年10月刊 |
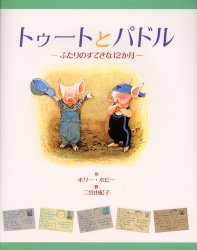 |
仲良しのこぶたのトゥートとパドル。ふたりは森の家に一緒に暮らしていましたが、ある日、旅好きなトゥートは世界大旅行に出かけることにします。家で日々の生活をゆったり過ごすのが好きなパドルはお留守番・・・。
トゥートは、パドルに毎月行く先々から冒険を伝える絵はがきを送ります。
旅に出たトゥートと森の四季を楽しむパドル。性格の違うふたりの日々は、どちらも素敵です。色々な生き方があっていいし、違うからこそ愉しい。離れていても友達同士でいられること、いつも自分らしく生きることの大切さを教えられます。
左ページに手書きのはがきでトゥートが語りかけ、右ページでパドルが答えるというスタイルの絵本です。ふたりの12カ月が透明感あふれる色調でやわらかに描かれ、絵を眺めているだけでも心が和みます。
メールや電話もスピーディーで便利ですが、相手のことを思いながら手紙を書く時間や、待ちわびていた手紙を受け取った時の喜びも、なかなか味わい深いものです。
作者のホリー・ホビーは米国の人気イラストレーター。この作品が初めての絵本で、続編も次々登場しています。
|
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]