としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2007年8月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 「世界陸上・大阪大会」にちなんで |
2007年8月25日から9日間の日程で、第11回世界陸上競技選手権大阪大会が開催されます。
そこで今回は様々な観点から「陸上」に関係する資料をご紹介します! |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| Paris 2003 世界陸上競技選手権パリ大会 |
| 新紀元社 2003年9月刊 |
 |
まずは、ずばり、世界陸上大会の資料から。
この本は、2003年第9回パリ大会の写真集です。
巻末には1983年第1回ヘルシンキ大会からの記録も掲載されています。
出版社にはもう在庫はないそうですので、図書館でご覧ください。
|
| |
| シルクロード9400km走り旅 ランニングシューズをはいた孫悟空 |
| 中山嘉太郎著 山と渓谷社 2004年4月刊 |
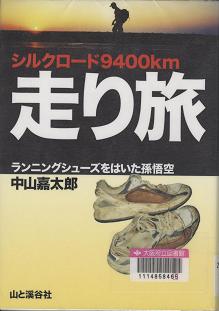 |
40歳を過ぎて突然会社を退職し、西安(昔の長安)からイスタンブールまで9400kmを、ウルムチまでの2700kmとウルムチ〜中央アジア〜イラン〜トルコまで6700kmの2回に分けて自分の足で走って旅をした記録。都合で車などに乗ってしまったときはできるだけ乗った場所まで戻って走りなおす徹底ぶりです。
さまざまな国を走っていく中で、時には体を壊したり、検問で役人にワイロを要求されたり、車と接触したり、暴漢に襲われたり、雪に悩まされたりとさまざまな困難にも遭遇します。その一方で、民家に泊めてもらったり、ご馳走になったりと人々の暖かさにも触れます。
著者はこの「走り旅」で2001年第6回植村直己冒険賞を受賞しました。
競技陸上とはまた違う「走る」ことの苦しみやよろこびがここにあります。
『走る人! 鹿児島-青森30日間2300キロ激走日誌』(岡崎圭著 吉備人出版 2006年3月刊)
『挑戦する脚 77日間オーストラリア夢大陸横断走り旅4200キロ!』(阪本真理子著 桜桃書房 1999年2月刊)
も、あわせてどうぞ。
|
| |
| 一瞬の風になれ 第一部 イチニツイテ 第二部 ヨウイ 第三部 ドン |
| 佐藤多佳子著 講談社 2006年8月刊 |
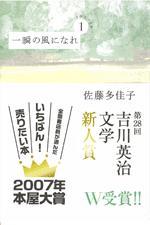 |
春野台高校陸上部。とくに強豪でもないこの部に入部した2人のスプリンター。
ひたすらに走る、そのことが次第に2人を変え、そして、部を変える――。
スポーツが得意な人も、得意でない人も、何かのスポーツを観戦していて、思わず引き込まれ、気付けば応援していたことはありませんか?そんな気持ちにさせてくれる陸上小説です。
生まれながらに恵まれた資質を持つ選手もいれば、努力しても夢に届かない選手もいる。それでもいじけない。恵まれていても驕らない。主役だけでなく、脇役までもがさわやかで潔い人物が多く、たんたんと進んでゆくストーリーなのに引き込まれます。全3巻。
第28回吉川英治文学新人賞受賞、2007年本屋大賞受賞。
2007年8月現在、予約多数のため、棚にはない状態ですが、大阪府立図書館でも所蔵しています。 |
| |
| ドーピングの現状・現実を語る (Sportsmedicine express) |
| 岡田晃編著 黒田善雄編著 ブックハウス・エイチディ 1990年3月刊 |
 |
人々に感動を与えるスポーツの祭典の影でドーピングの問題は後を絶ちません。薬物を使用した選手は制裁処分を受け、声援も記録も台無しになってしまいます。本書は「ドーピングとスポーツ」というシンポジウムの記録に追加資料を加えて作成された小冊子で、一般の方も興味を持って読めます。
より専門的なことを知りたい方は、『スポーツとアンチ・ドーピング』(全国体育系大学学長・学部長会編著 ブックハウス・エイチディ 1997年4月刊)も所蔵していますので、参考にしてください。 |
| |
| 世界トップアスリートに見る最新・陸上競技の科学 全10巻 (ビデオ)(書名の部分をクリックすると第1巻の書誌詳細表示画面にジャンプします) |
| 日本陸上競技連盟監修 ベースボール・マガジン社 1996年刊 |
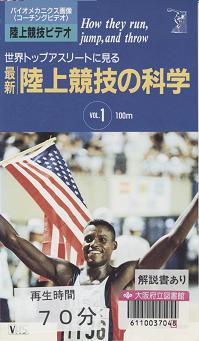 |
100m走、ハードル、砲丸投げ…。それぞれの陸上競技のフォームやスピードを科学的に分析したビデオで、各競技に携わる選手やコーチが分析結果を深く考え、自分の競技に生かせるような教材になっています。
と同時に、全く競技にご縁がなくても楽しめます。第10巻『ウォーミングアップ』 では、世界陸上の第3回東京大会で、当時第一人者カール・ルイス選手が、走幅跳で伏兵のマイク・パウエル選手に破れるシーンがあります。追いつ抜かれつの展開からパウエル選手に驚異的な世界新記録が出た後も、落胆せず集中を持続し、世界記録に比肩するすばらしい跳躍を何度も続けました。精神的・肉体的に自分の体を整えていく静かな過程をビデオは分析しており、競技場の盛り上がりと対比的で、実際に競技場に行って選手を追ってみたくなります。 |
| |
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]