としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2007年7月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| おばけ・幽霊・怪しのものたち |
日本の夏の風物といえば、涼を呼ぶ風鈴、かき氷、そして怪談。
愛らしかったり、怖かったり、個性いろいろの「怪しのものたち」。
図書館の本棚にも、たくさん見つかりました。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 百鬼夜行絵巻 妖怪たちが騒ぎだす |
| 湯本豪一著 小学館 2005年12月刊 |
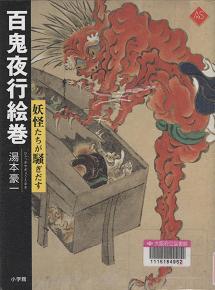 |
必ずしも夏限定で出現するわけではありませんが、日本の伝統的な「怪しのもの」といえば、まずは妖怪。そして幽霊。時代から時代へ、どんな風に伝えられてきたのでしょうか。
この本では、絵巻そのもののカラー図版のほかに、色鮮やかな地色を背景にして、さまざまな妖怪がアップで紹介されているのが魅力です。
ほかにも、
『妖怪図巻』京極夏彦文 国書刊行会 2000年6月刊
『妖怪図巻 続』湯本豪一編著 国書刊行会 2006年5月刊
では、絵巻の妖怪たちが生き生きと紹介されています。
また、
『幽霊名画集 全生庵蔵・三遊亭円朝コレクション』ぺりかん社 1995年7月刊
は、幽霊画の伝統的構図を広めたのはこの人とも言われる円山応挙の幽霊図に始まり、三遊亭円朝の髑髏図まで、さまざまな幽霊画50点を掲載しています。
|
| |
| 戦国時代のハラノムシ 『針聞書』のゆかいな病魔たち |
| 長野仁・東昇共編 国書刊行会 2007年4月刊 |
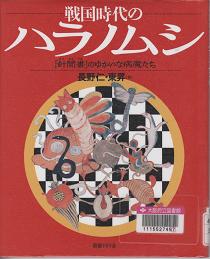 |
腹痛、腰痛、発熱から気絶、あくび、はたまた昼寝のし過ぎまで、戦国時代、病気という病気は体の中にムシがはいって引き起こるとされていました。
戦国時代に書かれた医学書『針聞書(はりききがき)』では、それらのさまざまな病気(?)とそれを引き起こすとされるムシたちの図と、その治療法が載っています。そこに登場するムシたちは、虫のようだったり、ケモノのようだったり、魚のようだったり、ヘビのようだったり・・・。
そんなちょっと可愛らしい、でもどこか不気味なムシたちを眺めていると、病気にはなりたくないけど、でもちょっと見てみたいとは思ってしまいます。 |
| |
| Don't Want to Go to Bed ? |
| ピーター・ハウレット訳 R.I.C.Publications 2004年1月刊 |
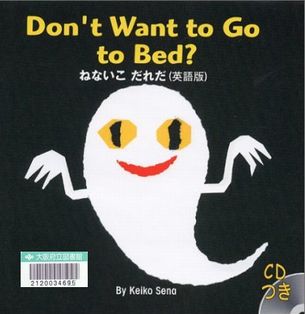 |
よなかに起きてる子は誰かな?こわいおばけに連れて行かれても知らないよ!
昔から親しまれている赤ちゃん絵本『ねないこ だれだ』(福音館書店 1969年11月刊)の英語版です。「おばけになってとんでいけ」のフレーズはどんな表現が使われているのでしょうか? 付録のCDと合わせてお楽しみください。
|
| |
| みぃつけた |
| 畠中恵:文 柴田ゆう:絵 新潮社 2006年11月刊 |
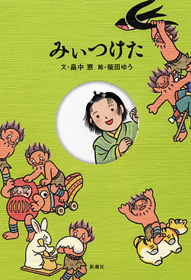 |
江戸有数の大店の若旦那・一太郎。身体が弱くて寝込みがちな彼は、他の人には見えないのに、なぜか家に住み着く小鬼(鳴家〈やなり〉)などが見える…
人気の『しゃばけ』シリーズの主人公、若旦那の幼い頃のお話のビジュアルブックです。このシリーズは挿絵も魅力の大きな一因。
今回はページをくるごとに、怖いようで無邪気でかわいい小鬼達が、絵になって画面いっぱい駆け巡ります。少しお疲れ気味の時など、ほんわか優しい気持ちにさせてくれる一冊です。気づかないけれど、あなたの家も、鳴家〈やなり〉が見守ってくれているかもしれません。
『しゃばけ』の世界に興味を持たれた方は、『しゃばけ』(新潮社2001年12月刊 をはじめ、最新作『ちんぷんかん』(新潮社 2007年6月刊)等、シリーズも多数出版されています。 |
| |
| 白石加代子「百物語」シリーズ 宵の1 宵の2 宵の3 (DVD) |
| 白石加代子出演 メジャーリーグ出版 2004年9月刊 |
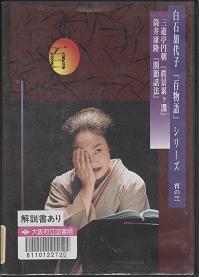 |
舞台の一人語りライヴのDVD(全3巻)です。
(ジャケット画像は、『宵の3 真景累ケ淵(しんけいかさねがふち)』のものです。)
お話の内容は「恐い話」「不思議な話」のみ。ライヴのテーマは「肉声における物語の体験」。小さい頃ママやパパに耳元で絵本を読んでもらった感覚で、どきどきわくわく、恐くて不思議な体験をしてみませんか。
ライヴがいかに恐くて魅力的か、登場作品の作家たちが「恐さ」への熱い想いを語る『恐くて不思議な話が好き 白石加代子の百物語』(赤川次郎[ほか]著 劇書房 1996年12月刊)という本もありますので、合わせてどうぞ。
|
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]