としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2007年6月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| うみのほん |
夏を先取りってことで、海についての本を選んでみました。
気が早いかもしれませんが今から予習を開始してみてはいかがでしょうか? |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 海の環境学習ハンドブック 海の魅力をもっと知ろう! |
| 大阪湾研究センター「海の環境学習ハンドブック編集委員会」編 国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所 2005年1月刊 |
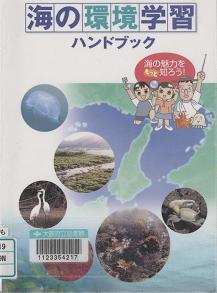 |
6月は環境月間。大阪でも、毎年「大阪湾クリーン作戦」など、環境保全活動が行われてきました。地元の海、大阪湾を知るには、まずこの一冊から!
バリバリの大阪弁のなにわん博士をはじめとしたキャラクターたちが、大阪湾の海水浴場や潮干狩りができる場所の紹介をはじめ、生き物や地形、漁業の歴史、海へ行くときの服装持ち物まで案内してくれる、いたれりつくせりの一冊です。
小学校高学年向けに編集されたハンドブックですが、たくさんのイラストや写真と、分かりやすい文章で、大人が読んでも楽しくてためになり、読み応えも十分です。読めば明日から、あなたも大阪湾博士?
|
| |
| 小さな帆船、大きな世界 大阪市帆船「あこがれ」世界一周航海記 |
| セイル大阪(財団法人大阪港開発技術協会)編 海文堂出版 2002年5月刊 |
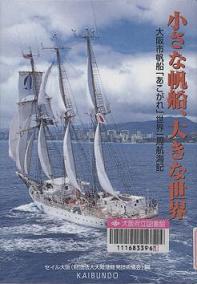 |
本書は大阪市が所有する帆船「あこがれ」による東回り世界一周の航海記録です。2000年に太平洋、カリブ海、大西洋、地中海、インド洋の大海原を横断。船上での生活や航海中に参加した帆船レースの模様が詳細に記されています。
カラー写真が満載の『帆船<あこがれ>ワールドセイル2000世界一周航海 公式記録集』(「帆船あこがれワールドセイル2000」推進協議会著 2001年3月刊)とあわせて、船と海の世界をお楽しみください。 |
| |
| 漂流物 |
| デイビット・ウィーズナー著 B・L出版 2007年5月刊 |
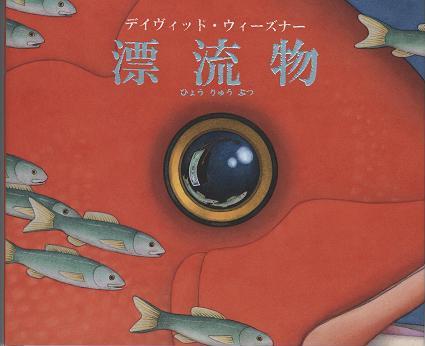 |
漂流物(ひょうりゅうぶつ)<FLOTSAM(英)>
海上や水上に浮かんでいて流れのままにただようもの 本文より
浜辺で少年が漂流物(・・・それはカメラでした。)を見つけるところからお話ははじまります。カメラの中のフィルムを現像してみると、そこには海底の花柄ソファに腰掛けて読書するタコ、海の中をまるで空を飛ぶように流れるハリセンボン製(?)気球・・・など。驚きの世界が広がります。数々の写真から少年は興味深い発見もします。
文字の出てこない絵本です。作者のウィーズナーは『セクター7』(B・L出版 2000年11月刊)や、『3びきのぶたたち』(B・L出版 2002年10月刊)などですでにご存知の方も多い実力派の作家です。想像力の幅広さと、確かな絵の力で、文字がなくても、むしろないことで、読者の年齢、国籍を問わない作品に仕上がっています。きっと読む人の数だけ、新しいお話がひろがることでしょう。想像力のままにお話の世界に浮かんで下さい。
この夏、海に出かける人も、都会で忙しく過ごす人も、ぜひ、ページをひらいてみて下さい。そこがどこでも、水の匂いと、夏の気配が存分に味わえる一冊です。
2007年コールデコット賞受賞。近日受け入れ予定です。興味のある方は、予約して下さい。
|
| |
| NHKスペシャル 生命 40億年はるかな旅 第3集 魚たちの上陸作戦 |
| NHK編集 NHKソフトウェア 1995年刊 |
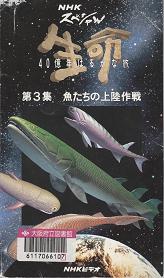 |
生命は海で生まれました。
海で生まれた生き物たちはどうやって陸に上がったのか。
このビデオは、残された化石から生き物たちの「上陸」の苦難の道のりをたどります。
3億年前の陸は、暑い。食べ物も乏しい。加えて重力に逆らわなければならない。その為に内臓を強化し骨を硬くし、上陸に備えていく。
生き物って常に前進しようとしてしまうんですね。
不思議だけれどエネルギーに満ちた前進の跡形、大きな宝庫、図書館へぜひどうぞ!
|
| |
| NAMI 梶井照陰写真集 |
| 梶井照陰写真 リトル・モア 2004年9月刊 |
 |
波は、潮汐や気候や気象、地形によって生じます。その形は一瞬一瞬で変化し、同じ姿は2度とあらわれることがありません。
この写真集では、そんな波の一瞬一瞬の姿を写しだしています。うねりのかたち、砕けるさま、波頭で飛び散るしぶきのかたち、岸にぶつかり砕けるさま、時刻や季節によって変化するしぶきの輝きや海の色・・・それはまるで彫刻のような、生きているような…。そんな海のもつ、美しさ、妖しさ、恐ろしさなどを感じてください。
静かな海がよければこちらをどうぞ。
"Hiroshi Sugimoto"(杉本博司写真 Kerry Brougher・David Elliott文 Hatje Cantz 2005年刊)
世界各地の海を、同じアングル同じフォーカスで写しているパートがあります。一見どれも同じ海に見えますが、じっと眺めているうちに、それぞれの海の個性が浮かびあがってきます。
|
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]