としょかんせんなりびょうたん
(資料紹介のページ)
2006年12月掲載 |
| ☆他の号はこちら としょかんせんなりびょうたんINDEX |
| |
| 新しい年へ |
| 大掃除や年賀状、おせち料理やお雑煮の準備などで慌ただしい年の瀬。新年を迎えるのにふさわしい本とCDを集めました。ぜひ手に取っていただき、どうぞ良いお年をお迎えください。 |
| |
| <書名(タイトル)の部分をクリックすると、蔵書検索の書誌詳細表示画面を見ることができます> |
| |
| 凧 |
| 茂出木雅章文 日本の凧の会監修 文渓堂 2002年3月刊 |
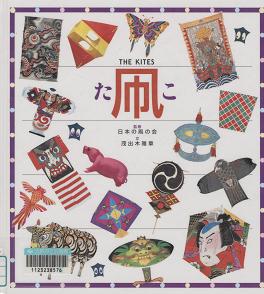 |
凧の歴史は、大変古く紀元前4世紀に中国で生まれたそうです。中国からヨーロッパをはじめアメリカにも渡り、ベンジャミン・フランクリンが嵐の中で凧を上げて、雷が電気であることを証明したことは有名です。日本でも鎌倉時代には凧上げ大会が催されたとか。大阪にも勝間凧と呼ばれる凧があったそうです。本書は、世界各地の凧の紹介に始まり、凧の作り方、凧の歴史などコンパクトにまとめられています。
今度のお正月休みは、子どもと一緒に自前の凧を作って、家族で凧上げ大会してみるのはいかがですか。
凧に関する資料はたくさんありますが、その一部を次に紹介します。
『やさしい和凧』(大橋栄二著 誠文堂新光社 1998年9月刊)
『大空を飛ぶ 飛行機凧』(長谷部光治著 誠文堂新光社 1984年10月刊)
『大空をゆく 帆船凧』(矢島盛男著 誠文堂新光社 1978年10月刊)
『凧をつくる』(広井力著 大月書店 1990年11月刊)
『凧大百科』(比毛一朗著 美術出版社 1997年12月刊)
『つくって揚げる゛かんたん凧″』(ビデオ)(日経映像 1996年12月刊)
|
| |
| 摺物 鴨川市所蔵藤澤衛彦コレクション 江戸の風雅な年賀状 |
| 城西国際大学水田美術館編集 城西国際大学水田美術館 2004年5月刊 |
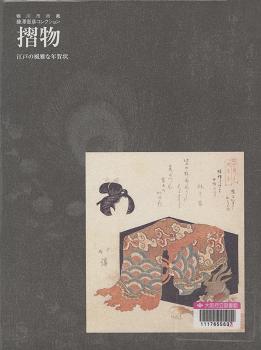 |
元旦の朝、郵便受けを「まだかな? まだかな?」と何度ものぞいた経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
この資料は、新年に交換された「摺物」が紹介されています。『「摺物」って何?』と思われた方は、ぜひご覧ください。本図録の鑑賞の手引きにわかりやすく紹介されています。双六や羽子板などの遊びも題材になっていて、眺めているだけでお正月気分が味わえます。残念ながら貸出できませんが、閲覧室で江戸時代のお正月にタイムスリップしてみませんか? |
| |
| 餅と日本人 「餅正月」と「餅なし正月」の民俗文化論 |
| 安室知著 雄山閣出版 1999年12月刊 |
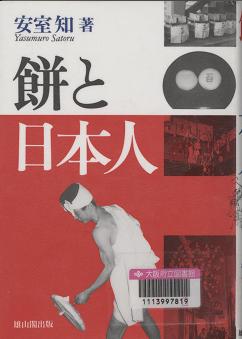 |
元旦に雑煮はつきもの」と思っている方も多いでしょうが、実は、元旦に雑煮を食べない地方もあるのです。
「餅正月」と「餅なし正月」を民俗学の視点から比較したこの本では、「餅なし正月」の実態や由来・伝承、餅の代用物など、さまざまに論じています。
儀式やハレの日など日本社会のあらゆる場で登場する餅と日本人のかかわりを論じた本書を、お正月にゆっくりお楽しみください。
|
| |
| 京の食文化展 京料理・京野菜の歴史と魅力 |
| 京都文化博物館学芸課編集 京都文化博物館 2006年3月刊 |
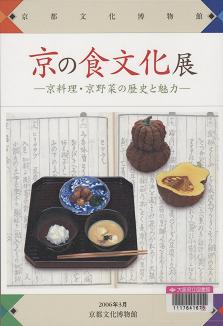 |
お正月。おせち料理にお雑煮と、料理も楽しみの一つですね。
「京料理」「食材」「行事食・伝統食」の三部からなる図版は、どれもきれいで、思わず「おいしそう!」と声をあげてしまいます。もちろん、元旦の献立や、お雑煮、掛鯛という正月飾りも紹介されています。
この本の表紙に使われている和綴じ本は大阪府立中之島図書館所蔵の『豆腐百珍』です。これの現代訳として、以下のものを中央図書館に所蔵しております。興味をもたれた方は、あわせてお楽しみください。
『豆腐百珍 江戸グルメブームの仕掛人』(何必醇原著 福田浩訳 教育社 1988年7月刊)
『豆腐百珍 江戸時代の珍本現代訳 』(何必醇輯 大曜 1985年1月刊)
|
| |
| きものの花咲くころ「主婦の友」90年の知恵 |
| 田中敦子編著 主婦の友社 2006年10月刊 |
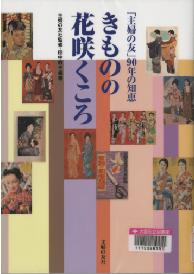 |
お正月くらいはきもので過ごそう、と決めていらっしゃる方も多いのでは。きれいな図版が多く、戦前戦後の女性ときものの変遷を楽しく読める一冊です。昔のほうがモダンな一面なども発見されて楽しいですよ。
『私のきもの人生』(宇野千代著 鎌倉書房 1985年5月刊)
きものを自由に楽しむ方が増えたように思います。太い帯をやめて、細帯を好きな布で作ったり、靴を合わせたり、帽子を被ったり。宇野千代さんは、そんな着方の大先輩でいらっしゃったようです。きもの本は最近たくさん出ましたが、まずはこれを。
『カワイく着こなすアジアの民族衣装』(森明美著 河出書房新社 2004年7月刊)
世界にはきもの以外にも、たくさんの民族衣装があるわけですが、なかなか自分で着るとなると情報が少ないもの。チャイナドレス、アオザイ、チマ・チョゴリ、サリーを中心に、実際の着付けから手入れまで書かれているこんな本もありますよ。
|
| |
| はつてんじん |
| 川端誠作 クレヨンハウス 2003年1月刊 |
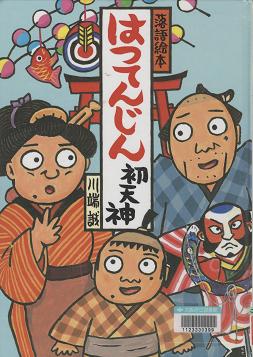 |
父と息子が、新年1月25日に天満宮で行われる縁日、初天神に出かけました。屋台を見て、次から次へとおねだりをする息子と応じる父の掛け合いが小気味良く描かれ、思わず微笑んでしまいます。
もともと上方噺であった「初天神」は、大正時代に三代目三遊亭円馬が江戸落語へと移し変えたもので、お正月によく披露される演目です。落語と絵本では、話の内容に少し異なるところもありますが、どちらも楽しめること請け合いです。
大阪天満宮では「初天神梅花祭」と称され、神饌に添えて梅の小枝をお供えするそうです。
同じ作者で、年末年始が題材の落語絵本『おにのめん』(川端誠作 クレヨンハウス 2001年4月刊)があります。
|
| |
| そらんじたい和歌170選(CD) |
| キングレコード 2003年5月刊 |
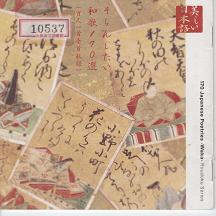 |
除夜の鐘を聞きながら年越しそばをたべて、初詣でのあとは、おせち料理にお年玉、みんなでカルタとり。今回は、そんな日本のお正月の風物詩のひとつ、小倉百人一首の全首に、上代から近世にかけての名歌70を加えた和歌朗読CDをご紹介します。
また、比叡山延暦寺の「除夜の鐘」から始まり、箏曲「春の海」など、日本の伝統的音楽がおさめられた『ベスト・オブ 正月』(CD)(ビクターエンタテインメント 2004年12月刊)は、なにかとあわただしい現代人に、ゆったりとしたお正月気分を味わせてくれます。
|
 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ] 中央図書館のページへ]
中央図書館のページへ] 大阪府立図書館のページへ]
大阪府立図書館のページへ]